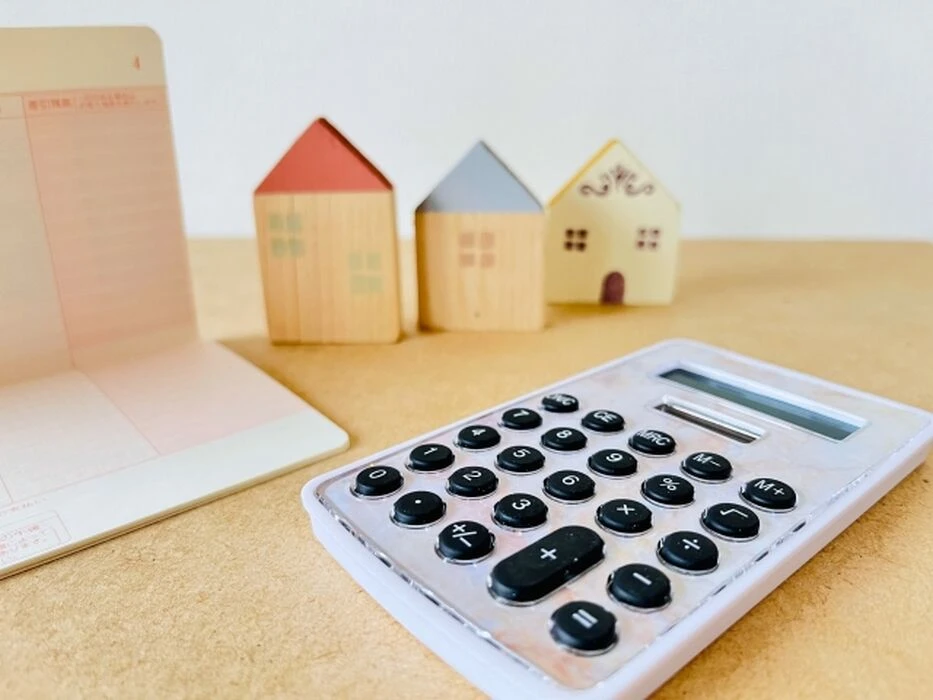不動産相続が発生したとき、相続人はさまざまな手続きを行わなければいけません。 また、税金に関する手続きもその1つで、こちらは相続手続きと同じく、場合によっては複雑な内容になることがあります。 ここからは、不動産相続と税金に関するポイントについて解説したいと思います。
相続税額の計算について
不動産相続を含む相続では、代表的な税金である相続税額の計算を行わなければいけません。 このときには、課税標準というものを使用します。 課税標準は、税額を計算するベースであり、課税標準に税率を適用して税額を計算します。 相続税の場合は、課税遺産総額をベースにし、こちらに法定相続分を適用した按分した、各人の法定相続分に応じた取得金額を課税標準として、超過累進税率を適用します。 ちなみに、相続または遺贈により、不動産を含む財産を取得した者が、被相続人の一親等以内の血族または配偶者のいずれでもない場合、その者には算出相続税額に2割を乗じた金額を加算します。
相続税と贈与税の関係について
不動産相続における代表的な税金である相続税と関係の深いものに、贈与税が挙げられます。 贈与税は、個人が個人に対し財産を贈与した場合に課される税金です。 税法の中に贈与税法という法律は存在せず、相続税法の中で贈与税に関する法規が定められています。 つまり、贈与税は相続税の補完税に位置付けられているということです。 もし、贈与税がなければ、不動産を含む資産が多い方は、生前に子どもや配偶者に贈与し、相続税の負担を減らそうと考えるかと思いますが、このような抜け道を防ぐために贈与税は設けられています。
相続税の申告期限について
不動産相続時に発生する税金である相続税には、申告期限が存在します。 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内とされています。 こちらの期限内に提出された申告書は、期限内申告書と呼ばれます。 また、災害などによってやむを得ない場合は、災害などの理由が止んだ日から2ヶ月以内に限り、申告期限を延長することができます。 一般的には個別指定といって、納税者が所轄政務所長に申請することで、延長が認められます。
準確定申告について
不動産相続を含む相続では、相続人が亡くなった被相続人の税金に関する手続きをしなければいけないこともあります。 こちらの手続きとして代表的なのが、準確定申告です。 所得税の確定申告は、毎年3月15日までとされていますが、年の中途に死亡した人の所得税は、その死亡したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が確定申告をしなければいけません。 こちらを準確定申告といい、その年の1月1日~3月15日までに死亡した場合で、亡くなった方が確定申告書を提出していないときは、亡くなった前年分と本年分をあわせて準確定申告を行います。 不動産相続に限ったことではありませんが、こちらの手続きは忘れがちであるため、相続人は注意しなければいけません。 ちなみに、相続人が2人いる場合は、連署による申告を原則としています。
延滞税について
不動産相続時に発生する税金である相続税について、納付期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに納税されなかった場合、延滞税が加算されます。 延滞税率は毎年変わり、そのときの情勢や景気によっては、大きく利率が上昇することもあります。 ちなみに、延滞税率は、短期プライムレートを基準に定められていて、こちらが下がると自動的に切り下げられます。 改定のタイミングは毎年12月15日で、財務大臣告示として官報に公表されます。
加算税について
不動産相続で発生する税金である相続税を少なく申告した場合や、不納付・無申告などがあった場合などは、加算税が課されます。 無申告に対してかかるのが無申告加算税、過少申告に対してかかるのが過少申告加算税であり、これらは自主申告した場合、税務署の通知、税務調査の結果などを受けて申告した場合とで、税率が変わってきます。 また、不動産相続などで発生した相続税について、事実の捏造や隠蔽などがあった場合には、無申告・過少申告税に替えて、重加算税というものが課されます。 こちらは、過去にもルール違反があった場合など、最大で50%にまで跳ね上がる非常に重い加算税です。 ちなみに、相続税の申告にあたり、重加算税が課されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。 ・通帳や契約書などの証拠書類を改ざん、偽造した場合 ・相続財産を隠したり、架空の債務を申告したりした場合 ・協力者を利用し、相続財産や債務に関する書類を偽造させたり、書類を破棄したりした場合 など
まとめ
ここまで、不動産相続と税金に関するポイントについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 税金が発生する以上、納税するのは国民の義務であり、よっぽどのことがない限り、避けることはできません。 また、納税の方法や期限なども細かく定められているため、相続人の方は、可能であれば相続が発生するまでに、ある程度の知識を持っておくべきです。